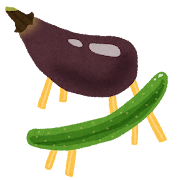「お盆=夏休み」
「お盆休み」が終わった。
小手指・三ヶ島の近隣地域は昔から蚕(カイコ)を飼い絹糸を地域産業としていた関係から、お盆は東京盆(一般のお盆の時期)より1ヶ月早いが、今は蚕(カイコ)は全く見ない。そういえば昔、夏休みの自由研究で蚕(カイコ)に桑の葉を与えながら繭(まゆ)になるのを絵に描いて記録していた記憶があるが、今はそんな自由研究のような夏休みの課題はあるのだろうか…?
昔のように「お盆=帰省して墓参り」という考えは薄れ、家族て休暇を楽しむ「お盆=夏休み」という生活スタイルに変化しているようだ。
全国での平均帰省率は26.0%という統計が出ている(総務省「社会生活基本調査」)ようだが、お盆に帰省するより家族旅行で楽しむ方が子供にとっては楽しみが多い。
元々、親の関係で引っ越しを重ねてきた私にはお盆時期に帰省する場所はもう無い。
生まれは新潟県六日町だが、もはや生家は無く、昔よく遊んだ魚野川や八海山が微かな記憶として残っているだけだ。冬場は雪囲いによって1階は昼でも薄暗く子供の頃は好きではなかったが、夏場は楽しかった。お盆で帰省した時はいつも曹洞宗の雲洞庵(うんとあん)という寺で虫を取り、魚野川(うおのがわ)で泳いでいたがもう何十年も昔のことだ。
「お盆」や「お寺やお墓」に関する考え方は日本古来からの文化なのかもしれないが、時代とともに考え方は合理的、現実的になってきている。古い考え方はダーウィンの「種の法則」と同様圧倒的少数派になっていくだろう…

 矯正をお考えの方はこちら
矯正をお考えの方はこちら